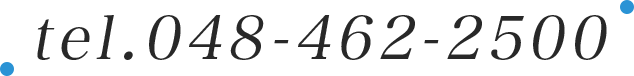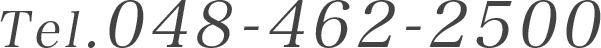歯科に行くタイミングって、どんな時?
2024年7月26日
皆さん、こんにちは。
7月も後半になり身体に堪える暑さが続いていますが、お変わりありませんでしょうか?
今日はスタッフから、なるほど〜と思ってしまった会話の一部より♪
スタッフ 「歯医者さんって行くタイミングが難しいですよね!」
私 「ん?それは、どう言うこと!?」
スタッフ 「矯正治療していた友人から、こんな質問を受けました。」
「気になったら、また来てね!って言われたんだけど、特に歯が痛いとか、気になる所もないし…でも矯正治療中は当たり前の様に定期的にクリーニングしてもらってたんだよねー。って言われて…」
私 「なるほど…確かに何かお口の中が気になって、来院した後から定期検診に来院する患者さんばかりかも…。」
毎日、患者さんが定期的な検診に来てくれる事が当たり前の様になっていた私に、患者さん側からの想いに気付かされた会話でした。
そこで、今日は「歯科に行くタイミングはどんな時なのか」をお伝えしたいと思います。
【歯科に行くタイミングとは?】
結論から言うと、今でしょ!!です。笑
今までもブログで訴えて来ましたが、特に歯が痛いとか、歯肉から出血するとか特に気になる事がなくても、定期的なクリーニングは必要です。
理由は、どんなに歯並びが綺麗で歯磨きが上手な方でも100%自分磨きでプラーク(歯垢)を取り除く事ができないからです。
微量であってもプラークが蓄積し残っている事で、虫歯や歯周病だけでなく全身的な病気に繋がってしまうからです!
期間としては3〜6ヶ月に一度、歯科衛生士によるプロフェッショナルケアや歯科医師による虫歯のチェックをする事で、ご自身の歯を健康的に維持させる一番の近道だと思っています。
是非、お電話で『クリーニング希望』とご連絡下さい!
平日は近いお日にちでもご予約頂ける日がございますので、学生さんは夏休みを利用して歯科検診をしてみませんか?
皆様からのご連絡をスタッフ一同、お待ちしております♪
※当医院も8/11〜17まで夏季休暇となります。