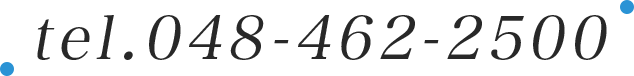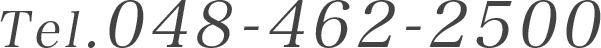歯科に行くタイミングって、どんな時?
2024年7月26日
皆さん、こんにちは。
7月も後半になり身体に堪える暑さが続いていますが、お変わりありませんでしょうか?
今日はスタッフから、なるほど〜と思ってしまった会話の一部より♪
スタッフ 「歯医者さんって行くタイミングが難しいですよね!」
私 「ん?それは、どう言うこと!?」
スタッフ 「矯正治療していた友人から、こんな質問を受けました。」
「気になったら、また来てね!って言われたんだけど、特に歯が痛いとか、気になる所もないし…でも矯正治療中は当たり前の様に定期的にクリーニングしてもらってたんだよねー。って言われて…」
私 「なるほど…確かに何かお口の中が気になって、来院した後から定期検診に来院する患者さんばかりかも…。」
毎日、患者さんが定期的な検診に来てくれる事が当たり前の様になっていた私に、患者さん側からの想いに気付かされた会話でした。
そこで、今日は「歯科に行くタイミングはどんな時なのか」をお伝えしたいと思います。
【歯科に行くタイミングとは?】
結論から言うと、今でしょ!!です。笑
今までもブログで訴えて来ましたが、特に歯が痛いとか、歯肉から出血するとか特に気になる事がなくても、定期的なクリーニングは必要です。
理由は、どんなに歯並びが綺麗で歯磨きが上手な方でも100%自分磨きでプラーク(歯垢)を取り除く事ができないからです。
微量であってもプラークが蓄積し残っている事で、虫歯や歯周病だけでなく全身的な病気に繋がってしまうからです!
期間としては3〜6ヶ月に一度、歯科衛生士によるプロフェッショナルケアや歯科医師による虫歯のチェックをする事で、ご自身の歯を健康的に維持させる一番の近道だと思っています。
是非、お電話で『クリーニング希望』とご連絡下さい!
平日は近いお日にちでもご予約頂ける日がございますので、学生さんは夏休みを利用して歯科検診をしてみませんか?
皆様からのご連絡をスタッフ一同、お待ちしております♪
※当医院も8/11〜17まで夏季休暇となります。
歯ぎしりにはスーパー大麦??
2024年7月18日
皆さん、おはようございます。
そろそろ梅雨明けでしょうか?
先日テレビである食材を食べると歯ぎしりが少なくなると言う興味深い内容を目にしました。
岡山大学の外山先生の研究グループが昨年の5月に発見したものだそうです。
歯ぎしりについては具体的な解消法は分かっておらず、対処療法としてマウスピースを入れたりして直接な歯と歯の接触をしない様にしているわけですが、歯ぎしりしてる人は国民全体の約7割くらいの方が歯ぎしりをしているそうで、主な症状として、朝起きると顎が痛い、歯が欠ける、顔が歪む、歯根破折(歯の根っこにヒビが入ったり、折れてしまう)と言った見た目や歯に直接ダメージが出てしまいます。
また歯ぎしりや噛み締めの力としてはおよそ100k gと言われ、食事でもせいぜい50k gと倍以上の力がかかっているそうです。
歯ぎしりすることで顎に痛み→睡眠の質低下→更に歯ぎしりへと地獄のスパイラルへ…
【食材で歯ぎしりが改善する? ある食材で歯ぎしりが軽減される!】
それは「スーパー大麦」です。
歯ぎしりする人、しない人を分析したところ1日平均の「食物繊維」の量が3g程度少なかった事が分かりました。
単純に足らなかった分の食物繊維を摂れば良いと言うわけではない為、少ない量でもしっかり食物繊維が摂れる、スーパー大麦はごぼうの約4倍の量とされています。また大麦だとスーパー大麦の半分のため、スーパー大麦が良いそうです。
【1日30g のスーパー大麦を1週間食べる事で歯ぎしりの回数、時間が減る効果が!】
まだ歯ぎしりに対して、ちゃんとしたメカニズムが分かっていないため、仮説との事ですが、食物繊維を摂る事で腸内の乳酸菌やビフィズス菌と言った善玉菌が迷走神経を介し脳に働きかけ、ホルモン分泌があがり、睡眠の質を改善させる事で歯ぎしりが減るのではないかとされているようです。
食物繊維を摂る事は、他にも便通改善やお肌の状態が良くなる等良いことばかり!
そして暑くて寝苦しいこの時期だからこそ、睡眠の質を上げ、免疫を下げない様にしたいところ。歯ぎしりや噛み締めがある皆さん、この夏は「スーパー大麦」を試してみてはいかがでしょうか。
睡眠の質を上げよう!
2024年7月11日
皆さん、こんにちは!
7月に入り猛暑日が続いていますが、
皆さん体調崩されたりはしていませんか?
夏バテを起こす要因はさまざまですが、睡眠不足は敵面だと言われています。
今日は歯科の内容から外れますが、睡眠不足になると、糖尿病や高血圧と言った病気のリスクも上げてしまうため、今日はこの時期とても大切な「睡眠」についてお伝えしたいと思います。
【カギは、脳を冷やす!室温じゃなく湿度!!】
昔から頭寒足熱と言われていますが、この時期は暑さと湿度から1年の中でも最も、睡眠の質が落ちる時です。
⭐︎質の良い睡眠を得るために☆
室内の湿度は40-60%が快適とされています。
例え、同じ温度でも湿度が高いと体感温度高くなり、熱中症リスクが上がります。
また、エスコンをつけて寝ると喉が痛くなると感じる方は、エアコンのせいではなく、口を開けて寝てるか、体が脱水しているから。
お口にテープを貼ったり、枕元に水分を置いておくと良いでしょう。
珪藻土マットを枕元に置くのもオススメ!
但し、昼間に乾燥させ、夜に湿度を吸ってもらえる様にしましょう。
⚫︎脳の温度を下げる
鼻呼吸は脳の冷却効果あり
鼻から吸って、息を7秒位止めて吐き出す。
冷却枕は体全体の体温を下げてしまうため、逆に睡眠の質を下げてしまいます。
⚫︎エスコンの設定温度は24-25度に
室温を下げ、冬用の布団をかけて寝る
脳は常に冷却が必要。夏バテは脳がカギ!
エスコンつけると朝のだるいのは、
コルチゾール(ホルモンの一種。分泌量が減ると免疫低下や不妊になる)がうまく働いていない、体内時計が正常運転していない、元々、睡眠不足がある等
布団の調整が必要!
【快眠法】
⚫︎長袖、長ズボンのパジャマ
吸収性、速乾性が高いポリエステル素材が◎
半袖短パンは汗を吸収したり、汗を吸収、蒸散できるため。
⚫︎寝る前に常温の水を
冷たい水だと体の深部体温を上げて逆に熱くなるからNG
トイレの心配がある方はチョビチョビ飲みをする
睡眠の質が上がれば、トイレ回数減ってくる
⚫︎氷枕は使用しない
首を冷やして体全体を冷やしてしまい、逆に睡眠の質を下げてしまう
脳を冷やすのは鼻から空気を吸って脳を冷やす事が大切
⚫︎エスコン、扇風機の風は直接あてない
一部だけ当たると汗腺が閉じて熱中症になりやすくなるから
⚫︎寝る直前までの飲酒は避ける
飲酒は利尿作用があり、脱水になりやすい
夕飯中に適量(1缶)楽しく飲む分には良い
【良い目覚め方】
⚪︎起床時、交感神経を優しく優位にすること
起きる時は、心地よい目覚めにしたいもの。
好きな人の声や歌、ニュースの音…等
ニュースの音は興味、関心で起きる事ができる。
逆に夜のニュースは内容によっては脳が覚醒するのであまり好ましくない。
⚪︎光で目覚め、起きる
夜は真っ暗にして寝ると熟睡
自動カーテン等で朝の陽の光を入れる
⚪︎除湿ではなく.冷房で
今のエアコンは温度を下げ湿度をコントロール機能があり、逆に除湿の方が電気代が高くなるとされている。
除湿の場合、口テープをして口の乾燥を防ぐ様に注意する。
身体を冷やさない様に寝る前に飲む水分は常温水にする
いかがでしたか?
この内容は朝の番組で睡眠のスペシャリストの梶本修身先生のお話でした。
私自身も睡眠の質を上げるために室温をコントロールしながら、羽毛布団で寝る事で夜中の途中覚醒が少なくなった様に思います。
この夏を乗り切るためにも、「睡眠」意識してみてくださいね!
歯の2大疾患〜虫歯&歯周病〜
2024年6月30日
皆さん、おはようございます。
ようやく梅雨に入りましたね…真夏日と言われる日も出てきました。
今年は「厳暑」と言われています。
急に暑くなると熱中症の心配がありますので、こまめな水分補給を心がけましょう。
今日は「歯の2大疾患」です。
先日、中学生になる息子が歯科検診を終え、保健便りを持ってきました。
その中にわかりやすく解説したものがありましたので、お伝えしたいと思います。
【なぜ、こうなった?虫歯と歯周病】
☆虫歯☆
虫歯は歯の表面(エナメル質)が溶けて、やがて穴があきます。
穴はエナメル質から象牙質へ、やがては歯髄(神経)へと進行すると激痛を伴います。
⚫︎なぜ、こうなった?
歯を溶かすのは「酸」です!
虫歯菌が食べ物の中の「糖」を使って「酸」を作るからです。
☆歯周病☆
歯肉や歯を支えている骨が壊されて、歯がグラグラ…放っておくと葉が抜け落ちる病気です。
⚫︎なぜ、こうなった?
歯周病菌の毒素で歯の周囲を攻撃します。
攻撃されたところは炎症を起こし、壊れていきます。
【原因は、どっちも同じだった!】
口の中の細菌がたまった物が「プラーク」
その中には、虫歯菌や歯周病菌が沢山います。
つまり、原因はプラークです。
プラークは歯磨きをしないと取れません!
【これって何で歯に良いの?】
☆食物繊維
干し椎茸、ごぼう、レタス、切り干し大根、きのこ類
よく噛むため、歯の表面をキレイにします。
☆噛みごたえのある食材
さきいか、みりん干し、たくあん、フランスパン
歯肉に刺激を与えて、歯周病を予防、また唾液が出るので、口の中がキレイになります。
☆カルシウムが多い食材
乳製品、小魚、大豆、小松菜
歯の質を良くします。
カルシウムの吸収を良くするビタミンDを一緒に摂るようにしましょう!
ビタミンDをが多い食材は魚介類やきのこ類です。
いかがでしたか?
中学生でも分かりやすく、また直ぐに取り入れやすい様な内容で感心してしまいました。
今日で6月も終わり。。。
しっかり食べて、暑い夏を乗り切りましょう!
笑いヨガ
2024年6月21日
皆さん、こんにちは!
急に真夏日の様な暑い日かと思ったら冷たい雨と寒暖差が激しい日が続いてますが、皆様、
体調崩したりしていないでしょうか?
またコロナ感染者が増加傾向とか、今年は劇症型溶連菌感染症が昨年1年間の人数を早くも上回る等のニュースで聞きますので、皆様もくれぐれもお気をつけ下さいね。
今日は「😆ヨガ」についてです。
笑いは「笑いのジョギング」と言われ、30秒笑うだけで、実際のジョギングと同じ効果があるそうで、笑うだけで、脳から気持ち良いと感じるホルモンが分泌します。
こんな天候だからこそ、元気に夏を迎えるためにも「笑いヨガ」をやってみてくださいね!
⚫︎歯磨き笑い⚫︎
口を横に伸ばして、「イッヒッヒッ」と笑いながら、歯ブラシを横に動かす。
大きな口を開けて「ハッハッハ」と奥歯を磨きます。
⚫︎うがい笑い⚫︎
口をふくらませ、できるだけ長く「ムグムグ」する。
水を思いっきり遠くに飛ばすつもりで「ブハッハッハー」と笑います。
⚫︎梅干し笑い⚫︎
世界一酸っぱい梅干しをたべることかを想像します。
酸っぱそうな顔をして「ハッハッハ」と笑います。
⚫︎ライオン笑い⚫︎
目と口を大きくひらき、思いっきり舌を出す。この時、体もライオン風に体現する。
そのまま「ハッハッハ」と大笑いで息を出します。
笑いヨガは周りの笑いが伝染して楽しく行う事ができますので、大勢で行うのがより良いと言われています!
是非、ご家族で、お友達とやってみて下さいね!
nico 2024.1月号より抜粋
100年時代を生き抜くために歯科からできること 〜糖尿病〜
2024年6月13日
皆さん、こんにちは!
梅雨入り間近でしょうか?今週は暑い日が続きそうですね。
今日は先日に続き、100年時代を生き抜くために歯科からできること…今日は糖尿病です。
当院のInstagramにも先日アップされてますが、歯科で血糖値が下がる?
皆さんはどう思いますか?
答えは、YESです!
【歯科と糖尿病の関係】
歯周病と糖尿病の関係については以前から言われていますが、
⚫︎糖尿病があると歯周病が悪化しやすくなる
免疫力の低下、血流不良、唾液が少なくなるなど歯周組織に障害により起こります。
⚫︎歯周病があると血糖値を下げるホルモンのインスリンの効きが悪くなる
歯周病治療を行う事で糖尿病の指標となるヘモグロビンA1cの値が最大1%減少すると言う報告もあります。
【なぜ、歯周病治療で糖尿病が良くなるのか?】
歯周病は細菌感染症です。
バイオフィルムによって歯肉が炎症を起こして破れた血管から出血し、血管内に異物(毒素)が体内に侵入します。
体に毒素が入る事でインスリンの効きを悪くさせる炎症性物質を作り出してしまいます。
また元々、肥満の方は内臓脂肪が多いため既に慢性炎症を引き起こしているために注意が必要です。
排除するためには、歯周治療を行い炎症性物質
が血管内に侵入しない様にすることで、血糖値の改善する可能性が出てくるのです。
一般的には歯周治療を行うとHbA1cが0.4%減るとされ、糖尿病薬1錠分に匹敵すると言われています。
いかがでしたか?
現在、日本には糖尿病または糖尿病予備軍が約2000万人、6人に1人に相当されると言われています。
食事、適度な運動を気をつけないと40代後半では誰でもなる可能性があるとも言われています。ここに歯の健康が入る事でより糖尿病リスクを減らす事ができますので、皆さんも歯科検診を定期的に受け、健康で元気に100年時代に立ち向かいましょう!
6月4日は虫歯予防デー
2024年6月2日
皆さん、おはようございます♪
6月になりました!
道端に可愛い紫陽花が咲いて、季節の進みを感じている今日この頃です。
6月最初の投稿は6/4の語呂に合わせて「虫歯予防デー」です。
【虫歯はなぜ、できる?】
虫歯になるには、いくつか条件が重なった時に、始めて虫歯になります。
その条件とは…
⚫︎歯の質
⚫︎細菌(ミュータンス菌)
⚫︎糖質
+
⚫︎時間
ですから、歯の質を高める様な歯磨き粉、洗口剤といったセルフケア商品を使い、日頃の歯磨きでしっかりプラークを取る様にフロスや歯間ブラシ(必要な方だけ)行い、食事、間食や晩酌といった嗜好品の摂り方を気をつければ、本来虫歯にはならないのです。
ですが…できてしまう…
それは、簡単に言えば
⚫︎歯磨きは1日1回未満
⚫︎甘いものをよく食べる
⚫︎ダラダラ、ちょこちょこ食べる
⚫︎口の中が乾く
この様な方は要注意!!
特に「口の中がよく乾く」は唾液が少ないから感じる感覚です。ですが、
実際は感じてなくても「口腔乾燥」を起こしている方がとても多く、コロナによる自粛、マスクの着用でより増えた様に感じます。
特にこれからの季節は、暑くなり水分補給が欠かせませんが、どんなものを飲むか。
また、水分を充分摂っていても、汗で水分が出てしまいますので、こまめな水分補給、そして歯磨きはもちろんのこと、定期的メンテナンスで自分では取りきれない細菌を取ってもらうことが大切です!
「口」は食事をするだけでなく、会話、呼吸…とても大切な器官の一つです。
是非、自分の「口」を改め、大切にして頂きたいたいと思います♪
100年時代を生き抜くために歯科からできること
2024年5月28日
100年時代を生き抜くために歯科からできること
〜口腔機能低下症〜
皆さん、おはようございます。
今日は生憎の雨ですね!夕方から夜にかけて雨足が強くなるみたいなので、気をつけてお出かけくださいね。
突然ですが…
皆さんは歯科と言うと、どんなイメージを持っていますか?
歯科と言えば虫歯、歯周病治療、矯正、ホワイトニング…いずれも「歯」に纏わるものです。
でも「予防」と言う言葉が出てきてからは、「治療」する人が減り「予防」する人が増え、80歳で歯が20本残っていれば良いという「8020運動」も今や半数以上は残っていると言われています。
今の日本は長寿国!平均寿命が右肩上がりです。
元気で歳を重ねられれば、それに越した事はありませんが、実際には介護年数が上がっています。
残念ながら男性は晩年9年、女性は12年は自立した生活を送れない=介助や介護が必要だと言われています。
具体的に言うと男性72歳、女性75才です。
だからこそ!
100年時代をどう乗り越えていくか!
今からやるべきことは何か!をお伝えできたらと思います。
【歯があれば食事は摂れる?】
皆さんはどう思いますか⁇
私は歯科衛生士ですが、恥ずかしながら数年前まで「歯があれば一生食べられる」と思っていました。
答えは✖️
歯があってもダメです。
噛んだ食物を「飲み込む」為には、
① 咀嚼(咀嚼)
食物を目や箸等で認知し、口の中に入れ「咀嚼(そしゃく)」をします。食べ物をこぼさない様に、口唇周囲の「口輪筋」で唇を閉じています。
口輪筋の力がないと、噛んだ食物をこぼしてしまいます。
② 舌圧
次に噛み砕いた食べ物を飲み込む為には、「舌」で食物を一塊にし、上顎に押し付け喉へ送る動きをします。
舌の動きが悪いと、いつまで経ってもお口の中で食物が残って飲み込めないのです。
③ 嚥下(嚥下)
最後ごっくんと食物を飲み込むには「嚥下(えんげ)」をします。
喉の周囲の動きがスムーズにできないと気管に入ったり、誤嚥性肺炎を招いたりしてしまいます。
この一連の動作をスムーズに行う為には、筋トレと同様に「口腔周囲筋」を鍛える必要があるんです。
私たちは毎日、このような当たり前の動作を行っていますが、当たり前にできなくなった時…食事は疎か会話も儘ならなくなります。
最近、ムセやすくなったな…
口の中が渇くな…
食べ物が飲み込みにくくなったな…という方は口腔機能が落ちてきているサインです!
それらを防ぐために!!
「口腔機能低下症検査」があります!
検査はかんたん!痛みを伴うこともありませんし、この検査は保険適応されていますので、3割負担の方でも1500円程度で行うことができます。
シノハラ歯科では、最後まで自分のお口から食事を摂る!ことを目標に歯の治療だけでなく、口腔機能低下症の検査を積極的に行っております。
100年時代をどう生きていくか!を考え、是非、検査を受けに、受けてみて下さい!
検査結果はもちろん、対策、トレーニング法をお伝えします!
ビタミンCパワー
2024年5月23日
ビタミンCパワー
皆さん、こんにちはー!
日に日に日差しが強くなってきましたね。
今年の夏も猛暑とか酷暑とか言われてしまうくらい暑くなるのか…と不安な私です。
暑くなると当然、汗をかきます。
汗と共に身体の外に出てしまうものがあります。その一つが、「ビタミンC」です。
【ビタミンCってどんな栄養素?】
ビタミンの仲間は数種類あり、身体の中に留まりにくい「水溶性ビタミン」と油物と一緒に摂ると身体に臼歯されやすい「脂溶性ビタミン」の2種類があり、ビタミンCは水溶性ビタミンに含まれます。また、ビタミンのほとんどは身体の中では、作られない為、食べ物やサプリといった物で摂るしかありません。
ビタミンはミネラル(無機質)と共に三大栄養素(タンパク質、脂質、炭水化物)の働きを助ける大切な栄養素です。
【ビタミンCの働き】
ビタミンCはコラーゲンの合成に必要不可欠で、皮膚や靭帯、骨、血管、角膜等を構成しており、健康や美容の維持に欠かせません。
またコラーゲンを作り、身体に吸収させやすくするには鉄も必要ですが、ビタミンCは鉄の吸収を良くしてくれます。
その他にも強い抗酸化作用(老化防止)や免疫機能の維持をしてくれています。
【ビタミンCが不足すると…】
ビタミンCが不足したら、すぐに具合いが悪くなる事はありませんが、徐々に体調は悪くなります。それでなくても現代人はビタミン欠乏が多いと言われていますので、意識して摂れると良いでしょう。
⚫︎肌トラブル
⚫︎動脈硬化
⭐︎歯肉からの出血(壊血病)
⚫︎貧血
⚫︎風邪をひきやすくなる
【ビタミンCを上手に摂る方法】
ビタミンCは熱に弱く、水溶性ビタミンのため
基本的には過剰摂取と言う事はあまり、考えなくても良いでしょう。
また熱に弱いため生で食べられる物は生で、火を通す場合はスープごと食べる様にしましょう。
〜ビタミンを多く含む食材〜
⚪︎アセロラ
⚪︎ケール
⚪︎ブロッコリー
⚪︎赤ピーマン
⚪︎いちご
⚪︎レモン
⚪︎キウイ
⚪︎柚子 等々
いかがでしたか?
ビタミンCは健康維持にとても大切な、食材ということをお分かり頂けたかと思います。
食後のデザートに、フルーツを食べるようにすると良いかもしれませんね♪
歯周病になったら、どうしよう…
2024年5月16日
皆さん、おはようございます。
爽やかな日が続いてますが、いかがお過ごしでしょうか?
日中と朝晩の寒暖差が大きく体調を崩している方が多い様なので、体調管理に気をつけてお過ごし下さいね☆
今日は歯周病についてです。
今までも歯周病については沢山取り上げてますが、歯周病は症状が出るまでに時間がかかる為、気づいた時には…なんてことも。
歯周病になったら、どうしよう…と思った方、必見です!!
【歯周病って、自分でも気づける?】
歯周病の初期は、歯肉の腫れや出血です。
よく、歯を磨くと血がでる。なんてことありませんか?
これを「歯肉炎」といい、歯周病の入口と言われています。
健康な歯肉は血が出たり、腫れたりはしないので、出血したら、もしかして歯周病かも…歯科へ受診することをオススメします!
【歯周病はどうやって進行するの?】
歯周病の原因はプラーク(バイオフィルム)と言われる細菌の塊です。
プラーク(バイオフィルム)は歯磨きで取りきれなかった歯の周りに停滞し、歯肉炎を起こします。
プラーク(バイオフィルム)を構成する多くの菌種の中に歯周病原細菌はLPSと言われる内毒素を出し、炎症性細胞を刺激して、サイトカインと呼ばれる様々な炎症性物質を放出させます。そして炎症が進行すると、骨を壊す細胞=破骨細胞の数が増え歯を支える周りの骨を一気に溶かしていきます。
残念ながら一度失ってしまった骨は戻ってはきません。
また歯周病は全身の病気との関連性があり放っておくのは大変危険です。どんなぬ歯磨きが上手な方でも、自分磨きで100%プラークを取り除く事はできないので、半年に一度は歯科へ受診しプロによる口腔ケアをしてもらいましょう。