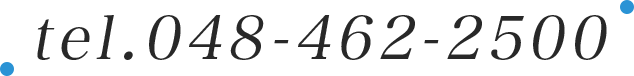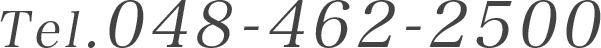ストレスが原因⁈お口の病気
2025年3月27日
皆さん、おはようございます!
急に暖かくなり、桜が一気に咲き始めましたね♪
3月も終わり…4月から新しいスタートを切る方もいらっしゃるかと思いますが、まだまだ寒暖差が激しい時期なので体調崩さないように気をつけてお過ごしくださいね。
今日は「ストレスが原因⁈お口の病気」です。
【ストレスがもたらすお口の影響】
ストレスが加わるとお口にも変化が出てきます。
例えば…
•食いしばり
•歯ぎしり
•頭痛
•肩こりや顎の痛み 等々
そして、このような状態は自律神経でいう交感神経が高まっているので唾液分泌が落ちてしまいます。そうすると、唾液は身体の中からできる免疫なので体調を崩しやすくなってしまうのです。
【どうすれば良い?改善方法】
ストレスの元凶を取り除く!これができたら1番良いのですが、難しいのが現実です。
◉先ずは噛み締めから意識して外していきましょう!
人間は食事以外の時間はお口を閉じていても奥歯が当たらないように安静時空隙と言って数ミリ隙間が開くように出来ています。実際、1日の中で奥歯が当たる時間は15分程度と言われています。
ですが、それが何らかの要因で奥歯が当たっていたら、それは噛み締めていることになります。
ご自身の目につく場所に食いしばらないと書いたメモを貼ったり、目印になるような物を置いて、それが目に入ったら意識して噛み締めていないかを確認、もし噛み締めていたら外すようにしましょう!
◉寝る時のマウスピースを入れてみる
保険治療で作ることができますので、一度先生に診てもらうと良いでしょう
◉痛みを伴う場所をマッサージする
頭痛や肩こりの場合は歯科だけでは解決できないこともあるかもしれませんが、ストレッチをしたりお風呂で身体を温めた後にマッサージを行う事で血流がアップし改善するかもしれません。
◉舌を回して唾液分泌量をアップさせる
舌は筋肉の塊です。初めは疲れるかもしれませんが、徐々に慣れてきます。
また舌を回す事で唾液腺が刺激され唾液量がアップします。
いかがでしたか?
新年度となる4月まであと少し…身体の不調は少しでも取り除いていきたい物ですね。
まずはご自身が噛み締めたりしていないかを知ることで解決策が見えてくるかと思います。皆さんも是非、意識してみてくださいね。
歯の役割いろいろ
2025年3月23日
皆さん、おはようございます!
昨日は風が強かったものの、昼間は暖かかったですね!桜の蕾もだいぶ大きくなってきましたので、そろそろ開花宣言が出るのではないでしょうか?今からとても楽しみですね♪
今日は「歯の役割」についてです。
【歯は噛むだけでない!色々な役割がある】
歯は大きく分けて
◉咀嚼(そしゃく)
◉発音
◉顔面形成
があります。ですが他にもたくさんの役割を果たしています。
特に良く噛むことで得られる「ひみこのはがいーぜ」をご紹介します♪
⚪︎ひ: 肥満予防…良く噛むことで食べ過ぎを防止し、結果的に肥満防止に繋がります。
⚪︎み: 味覚の発達…食べ物の形や固さを感じることができ、味も分かるようになります。
⚪︎こ: 言葉の発達…口の周りの筋肉をしっかり使うため、顎の発達や表情が豊かになる等、発音が綺麗になったりします。
⚪︎の: 脳の発達…脳の血流が良くなることで、子供は脳が発達し、大人は物忘れ防止に繋がります。
⚪︎は: 歯の病気予防…良く噛むことで唾液量がアップします。それにより、虫歯や歯周病から守ります。
⚪︎が: ガン予防…唾液の成分にペルオキシターゼという酵素が食品の発がん性を抑える効果があります。
⚪︎いー: 胃腸快調…消化を助けたり、胃腸の働きを活発にします。
⚪︎ぜ: 全力投球…身体が活発になり、仕事や遊びに集中できます。
いかがでしたか?
歯の役割にはたくさんの意味があり、特に「良く噛むこと」で、体全体に良い効果があることが理解いただけたかと思います。
良く噛むためには、時間をかけて食事を楽しむこと、また、飲み物で流し込まないようにすることが大切です。
•クリニカHP参照
誤嚥性肺炎って知ってる?
2025年3月13日
皆さん、こんにちは!
今日は朝から暖かいですね♪
ですが…花粉症の方は今がピークではないでしょうか?
今日は「誤嚥性肺炎」についてです。
【誤嚥性肺炎とは?】
食べ物や唾液が気管の中に流れ込んで肺に感染を引き起こす病気で、高齢者に多いと言われていますが、近年では口腔機能が落ちた方も誤嚥性肺炎一歩手前になることもあるとか。
特に高齢者は嚥下機能や反射機能が低下し就寝中に誤嚥性肺炎を引き起こしやすくなります。
誤嚥性肺炎の予防には年齢や健康状況あった「お口のケア」がとても大切になっていきます。
【誤嚥性肺炎の予防は!?】
それは、口腔内を清潔に保つことです。
ただ歯を磨くだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを用いて歯垢を。磨けない方はスポンジブラシやウエットシートで歯の表面に付いている食べカスをしっかり取り除くことです。
また、「舌」のケアも忘れずに!!
歯を磨く際、鏡の前で舌をベーッと出してみましょう。
白くなっていたり、色がついていたりしたら、舌ブラシで刮ぎ取りましょう!
これは「舌苔」と言って舌の表面の凸凹している間に細菌が付いていて口腔寒気を悪くさせるだけでなく、口臭の原因にもなりますので、寝る前に歯磨きの際は舌のチェックも忘れずに!行いましょう。
デンタルフロスの使い方
2025年3月7日
皆さん、こんにちは!
3月になりましたが、雪が散らつく今週でしたね。
早く桜の開花が待ち遠しいですね。
今日は「デンタルフロスの使い方」についてです。
毎日歯磨きはするけど、デンタルフロスはたまーに使う、歯と歯の間に詰まった時に使う、毎日使うけど、ただ歯と歯の間に入れるだけ等、毎日ちゃんと使えてる方が少ないなと感じます。
では正しいデンタルフロスの使い方とは
どう使えば良いかお伝えします。
【デンタルフロスを使うのは歯を磨く前!?それとも磨いた後!?】
食べカスやプラークを取る意味でもら磨く前がよいでしょう。
それは歯と歯が接触してる、重なってる部分は歯ブラシては磨く事ができないからです。
この時フロスの通し方として歯と歯の間にノコギリを引く様に前後に、そして上下に動かすことがポイントです。
ただフロスを入れて引き上げるだけでは充分に取れないからです。
その後、歯ブラシで全体的に磨きましょう!
【デンタルフロスを上手に使うポイント】
よく皆さんから、フロスを通しているが奥歯は難しくて入れられない。とかフロスが奥歯は入らない。なんて言われることがあります。
それにはフロスを巻き付ける指とフロスの長さにあります。
まずデンタルフロスのケースから肘の長さくらい(30-40センチ)を取ります。
そして巻き付ける指は「中指」です。
人差し指に巻き付ける方が多いですが、人差し指だとコントロールしにくいため中指に巻き付けましょう。
フロスを歯と歯の間に2〜3ミリずつ、ノコギリを引く様に前後に動かしてから、上下に動かしましょう。
その後、お口を濯いでから歯ブラシに歯磨き粉を付け全体的に磨きましょう。
濯ぐ時、歯磨き粉の有効成分が洗い流されない様に軽く1回だけにすると良いと言われています。
いかがでしたか?
デンタルフロスの使い方を改めてお伝えしましたが、実は一番難しい所は習慣化だと思います。
歯を磨く際は歯ブラシ+デンタルフロスは必須!と頭にインプットできれば良いですね!